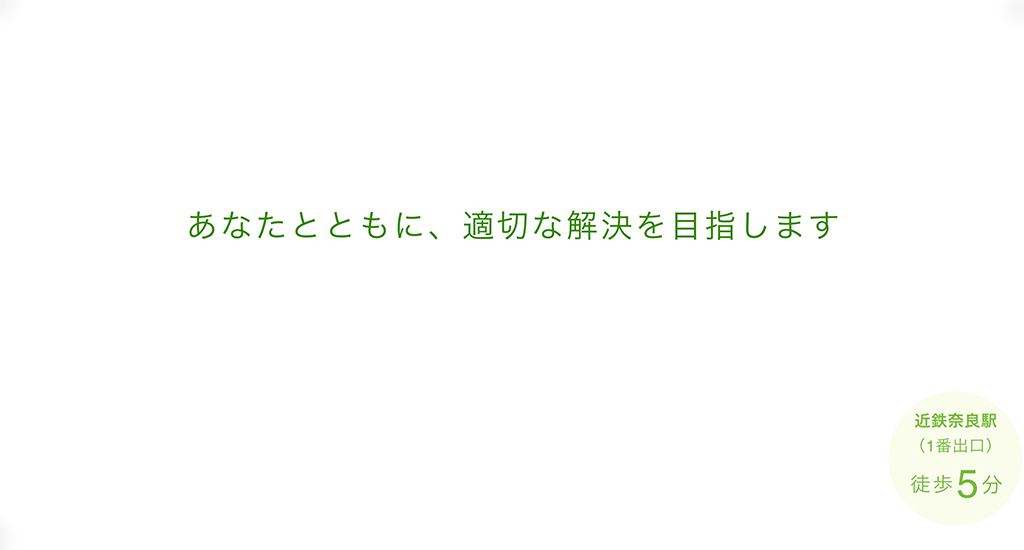ご予約、ご相談随時受付中です。
当事務所の特徴




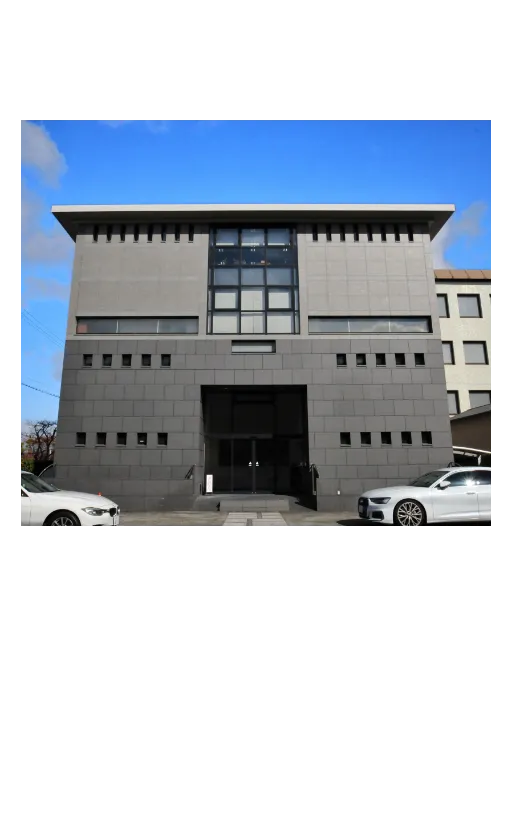
ご挨拶
現在、当事務所には10名の弁護士が在籍し、それぞれの知見や経験を活かしながら、依頼者の皆さまに最適な法的サービスを提供しています。
相続に関するトラブルは、親族間の感情のもつれを伴うことが多く、大きな精神的負担となりがちです。当事務所では、依頼者の皆さまの権利と利益を守るため、一つ一つの案件に真摯に向き合い、最善の解決策を追求してまいります。
どのようなご相談でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ



よくある質問
-
Q[質問: 1]Q1. 遺産分割をするためには何を把握する必要がありますか?
相続人の間で遺産の分け方を話し合って決めるためには、まずは、①相続人、②遺産の範囲(不動産、預貯金、有価証券など)、③遺産の評価額、④遺言書の有無、内容、を把握する必要があります。
-
Q[質問: 6]Q6. 遺産分割協議がうまくいかない場合、どうすれば良いですか?
遺産分割協議が進まない場合、一般的に、相続人間で紛争化しておりこれ以上話合いでは解決しないケースが多いため、一つの手段として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。
もっとも、事前の準備なく、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることはお勧めしません。
遺産分割調停は、裁判所の手続きではありますが、あくまで相続人間での話合いによる解決を前提としますので、予め紛争の原因や解決すべきポイントを整理したうえで遺産調停に臨まないと、感情的な縺れと相俟って、解決まで長期化してしまう恐れがあります。
遺産分割調停を申し立てる前に、ご相談いただけましたら、当事務所の担当弁護士が見通し等をご説明させていただきます。
なお、Q1の①から④までの事項について、事前に情報を整理していただけるとご相談時にスムーズに具体的な話に入ることができます。
-
Q[質問: 7]Q7. 相続放棄はどのような手続きが必要ですか?
家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしてこれを受理してもらう必要があります。
-
Q[質問: 8]Q8. 相続放棄はいつまでに家庭裁判所に申し立てる必要がありますか?
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った」ときの目安としては、被相続人の死亡日や、相続人自身が被相続人が亡くなったことを知った時(市役所から相続人代表者指定届が届いた時など)だとお考えください。
-
Q[質問: 18]Q18. 遺留分を侵害された場合、どのように対応すべきですか?
遺留分侵害額請求は、相続開始日(被相続人の死亡日)および遺留分を侵害されたことを認識した日から1年以内に行わなければなりません。
請求期限が非常に短いため、請求に関する詳細な対応方法については、弁護士に相談することをお勧めします。